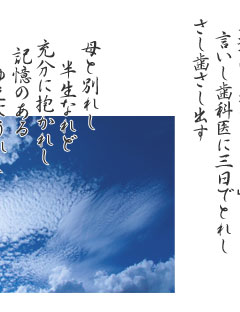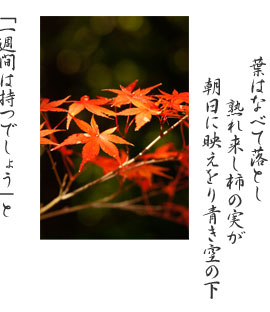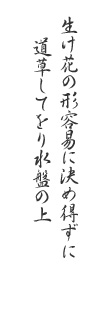●女将のエッセイ/もじずりの花
大西民子は花を詠った短歌が多い。自分の分身のように花を詠い、花に心を織り込んでいる。
花と生き様を重ね合わせる短歌と言えばやはり大西民子が浮かぶ。
ミモザ、クローバー、薔薇、玉すだれの花、蓮の花、かたくりの花、卯の花、ダリア、ひるがおの花、合歓の花、コスモスなど花と心の織り成す短歌が胸に沁みる。
大輪の立派な花ではなく、なにげない小草花に思いを馳せている。
なすことのなべてよぢれてゆく如き思ひに仰ぐもじずりの花
もじずりの花はねじばなとも言われ、ラン科の多年生植物。夏に薄紅色の小花がねじれた穂になって咲く。草の中にははえていて、気づかないときさえある可憐な花だ。
自分のすることが自分のすることが自分の思う方向には進まず、ねじれるような感覚を待つことがあるがそれをもじずりの花と重ねている。同じ歌集の中で、
つぎつぎに朱の色を噴くサボテンの花の速度にわれは及ばぬ
と言うのがある。静かに朱の花を咲かせていくサボテンに、眩しきものを感じ、花の速度に脱帽していると同時に、自分の体力的な衰えと対比している。
肉厚な緑色のサボテンから色鮮やかな花が咲き続けるのを、朱の色を噴くというのが鋭い。
道のべの紫苑の花も過ぎむとしたれの決めるたる高さに揃ふ
「人間を超える世界を虚心に見直したい」という思いで生きて来られたようだ。
人間は自然の前に抗うことができず、弱き者。
ただ、無心に淡々と生きようという思いが感じとれる歌だ。
紫苑はどうして同じ高さに揃っているのか、植物にも、人工ではできない法則や摂理があり、人間というちっぽけな存在を見せ付けられた瞬間なのだ。
大西民子の歌は花でさえ人生観を詠いあげている。